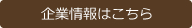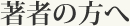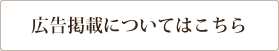無料版・バックナンバー
- ビジネス選書&サマリーのバックナンバーをご覧いただけます。

2002/04/19
成果主義は怖くない
-

成果主義は日本企業の大きな潮流になりつつあります。でも結果がすべてに優先するといったイメージで語られるのも事実です。本書は人材マネジメントの専門家が、成果主義の真実と、社員はそれにいかに処すべきかについて解説します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■
■■ ビジネス選書&サマリー
http://www.kfujii.com/TCY02.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【読者数8696部】━
=今週の選書=
■成果主義は怖くない/高橋俊介■
プレジデント社
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■
■■ 今週のサマリー
■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
成果主義は日本企業の大きな潮流になりつつあります。でも結果がすべてに
優先するといったイメージで語られるのも事実です。本書は人材マネジメン
トの専門家が、成果主義の真実と、社員はそれにいかに処すべきかについて
解説します。
【1】
これからの企業は一握りの人間が知恵を出し、大多数の人が汗を流すのでな
く、より多くの人が知恵を出し、それが利益を出す組織でなければならない。
つまり個人の知的生産性の向上が課題である。大切なのは、個人の自立であ
り、会社がそれをいかにサポートするかである。それが企業の存亡を決める。
従来のように会社が社員のキャリアを支配し、その代償として終身雇用を保証
するようなやり方では成果が上がらない。キャリアも個人主導で作り、それを
会社が支援すべきだ。
自分でやりたいことを考え、提起し、責任をもって成し遂げる。会社はそれを
正当に評価する。こうして知的生産性を高めることが、これからの成果主義の
課題である。
【2】
成果主義にはさまざまな誤解がある。まず目的が違うことがある。単なる人件
費の削減の隠れ蓑になっているケースがよくある。
また目的は合理的でも、方法論が違うケースがある。この場合、途中で誤った
方向に行ったり、後に様々な弊害が出るケースがある。
成果主義だけですべての問題を解決しようとするケースもある。要は自分の会
社で起きている成果主義がどの類のものか明確にしておくことが重要だ。
問題のない人事制度などありえない。むしろ問題のありどころやそのレベルを
把握、その中でいかに自分のキャリアを形成していくべきかを知るべきなのだ。
【3】
もしあなたの会社でジョブサイズという言葉が出てきたら要注意だ。これは
仕事を詳細に分解・数値化し、等級を当てはめ給与を決めるやり方だ。
つまりポストや机に値付けするものであり、どれだけ仕事をしたかでなく、組
織内のポストの「偉さ」の度合いを測る仕組みである。
また事前に個人の仕事を詳細に定義、評価しないと人事制度が運用できなくな
る。だがこの激変の時代に仕事の詳細を事前に決めておくことなど不可能だ。
こうして制度は形骸化する。またヒエラルキー重視の傾向が強まる。さらに仕
事の定義がどんどん詳細化し、結果的に自立的で柔軟な組織の構築どころでは
なくなる。
【4】
成果主義は「金で人の頬をたたいて働かせる仕組みだ」と考えるのは誤解だ。
人間が仕事をする要因には、なければ不満が出るが多くてもやる気が上がる
わけでない"衛生要因"と、あるほどやる気が高まる"満足要因"がある。
賃金は衛生要因であり、一定以上増やしてもやる気が出るわけではない。
特に成果主義で知的生産性を高めるには、やりたいことをやり成果を出し、
会社に貢献したことに対して給与を与えるべきである。
つまり成果主義における給与とは、組織に対して社員が投資した"知恵"に
対する配当と考えることができるのだ。
【5】
成果主義の時代に個人はどう生きるべきか。これからは会社に一方的に振り
回されるのでなく、自分でキャリアをデザインしていくことが大切だ。
その際、大切なのは自分の評価基準だ。これまでの基準は、出世という会社
が作ったものだった。しかし、それは会社を一歩出れば何の役にも立たない。
かといって、資格や特殊技能も考えものだ。激変の時代「これができれば、
あなたは大丈夫」などというものはない。
これから必要なのは自己基準だ。ただし報酬と幸福度の間には相関関係はな
いので、それ以外のところで、いかに自分の基準を持つかが問われている。
また先の読めない現代、ゴールや計画を明確に持つことはできない。これから
は「どんなキャリアを歩めれば自分は幸せなのか」というキャリアに対する
"ビジョン"とそれを測る"自己基準"が最も重要になるのだ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■
■■ 今週のコメント
■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
激変の時代です。当然仕事のあり方はどんどん変化しています。旧い枠組みで
決められた仕事の中身なんて、どんどん変わってしかるべきです。
雇用不安が起こると、ブームになるのが資格です。私もサラリーマンのころ、
保険のつもりで"中小企業診断士"の資格を取りました。現在も勉強している
人はたくさんいるようです。
ところでそいういう皆さんは、この仕事はどんな仕事だと思ってますか?一般
に中小企業のコンサルティングと言われてますが、じゃあコンサルタントの仕
事って何でしょう?
とって始めて気づいたのですが"診断士の仕事"なんてないんですね。もちろ
ん企業の問題を解決して、成果をあげてもらうことを目指します。ですがその
アプローチは、人によって、また相手、タイミングなどによって様々です。
私も最初のころは、仕事を杓子定規に考えていました。「これってコンサルタン
トの仕事じゃないよな」と悩んだり、仕事を断ったりしたりすることもありま
した。
でも、最近はやりたいことを、やりたいようにやればいいと思っています。こ
れをかき集めて「藤井式コンサルティングだ」と勝手に思っています。コンサ
ルティングと呼べなくなれば、他の呼び名を考えるだけです。そのほうがずっ
と楽しいし、成果も上がることに気づいてしまったからです。
サラリーマンもそうですよね。もはや決められた仕事を、決められたとおりに
やるだけでは会社に貢献できないでしょう。営業だからこの仕事、部長だから
この仕事、なんてありえません。仕事は、組織や肩書きや資格が与えてくれる
ものではないのです。
大事なのは、会社がこれをしっかり評価できるかどうかです。どんな形であれ、
会社に利益をもたらした人を正当に評価できることが、本当に強い会社をつく
るのです。皆さんの会社は、いかがでしょうか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━