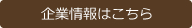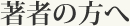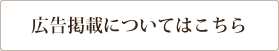無料版・バックナンバー
- ビジネス選書&サマリーのバックナンバーをご覧いただけます。

2009/02/23
上司の教科書
-

上司の世界に何が起きているのか?上司が新しい悩みを抱える時代が到来した。組織のフラット化が進み、従来のようにマネジメントさえしていれば事足りるマネージャーなどほとんど存在しなくなった。
プレイングマネージャーとして自分自身の目標に数値が設置されると同時に、率いるチームの目標数値を達成しなければならない姿が一般的だ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■
■■ ビジネス選書&サマリー
■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<読者数61,610部>━
■今週の選書
■上司の教科書
■石山恒貴/洋泉社
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★本書の詳細、お買い求めは、
→ http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4862483658/tachiyomi
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆【弊社広告】大半がリピートされる優良媒体です。
→ https://www.bbook.jp/advertisement.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■■選書サマリー
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上司の世界に何が起きているのか?
【1】
上司が新しい悩みを抱える時代が到来した。組織のフラット化が進
み、従来のようにマネジメントさえしていれば事足りるマネージャ
ーなどほとんど存在しなくなった。
プレイングマネージャーとして自分自身の目標に数値が設置される
と同時に、率いるチームの目標数値を達成しなければならない姿が
一般的だ。
そんな中、部下の状況を知りたくても、部下は報告にきて話そうと
せず、メールによる報告ばかり。飲みに誘っても断られる。
このような状況で、どのように部下とコミュニケーションをとれば
いいのか頭を悩ませている。解決策の一つが、部下を幸せにするリ
ーダーシップだ。
といっても、実際には、むしろマネージャー自身に、より大きな利
益をもたらす。部下が元気になり、チーム力が高まることで、マネ
ージャーのリーダーシップ開発につながるからだ。
【2】
マネージャーが抱える新しい悩みの根本原因は、たくさんあるが、
底流にある変化の方向性は共通している。「以心伝心の崩壊」だ。
「空気を読め!」という発言に象徴されるように、かつて日本の組
織では、各人が場の空気を察して動いていた。だが、日本の職場で
も、次第にこれが通用しなくなりつつある。
もちろん、空気を読むことを重視する文化の根本は変わっていない。
だが、職場での大きな変化の底流に「以心伝心の崩壊」があること
はほぼ間違いない。変化をもたらした要素は、大きく5点ある。
第1の変化は、社員が異を唱えはじめたことだ。「仲良しクラブ」
と呼ばれるように、これまでは終身雇用や年功序列などがあり、部
下がマネージャーに異論を唱えることは昇進に有利でなかった。
しかし、90年代以降、雇用調整が一般化し、成果主義の進展で評価
が短期間で判断されるようになった。またプライベートを尊重する
若手社員の意識変化も進んだ。
会社と個人の関係が変化した結果「仲良しクラブ」でいるメリット
を社員が感じなくなった。そのため、異を唱えることにためらわな
い企業文化が生まれたのだ。
【3】
2番目の変化は、企業の構成員の変化だ。かつては男性正社員を中
心に単一集団で仲間意識を共有できた。だが、今では女性が台頭し、
契約社員や派遣社員などの非正規従業員や外国人も増えた。
企業は、単なるコスト削減でなく、社内の活性化を意図して構成員
に多様性を持たせるようになっており、人材の多様化傾向は、ます
ます進むはずだ。
こうなると「同じ仲間ではないか」という合言葉だけで、社員の働
く意欲を喚起することはできない。短期間で急速に成長することを
後押ししてくれないマネージャーは、相手にもされないのだ。
マネージャーにとって、今や職場の多様性のマネジメント、すなわ
ちダイバーシティマネジメントは、必死に取り組むべき厳しい課題
になっているのだ。
【4】
第3の変化は、マネージャーの知識・経験・スキルと、勤続年数と
の相関関係が弱まってきていることだ。
技術革新の変化の早さやソリューションビジネスにおいては、現場
の部下に重要な知識・情報が集約されやすくなった。そのため、マ
ネージャーが知識を武器に「ついてこい」と言えなくなったのだ。
第4は、組織のフラット化が進み、部下の管理だけでなく、自らも
業務を遂行しなければならくなったことだ。その結果、マネージャ
ーはますます多忙になり、部下への対応が難しくなったのだ。
5番目は、法的対応における常識の変化だ。現代のマネージャーは、
セクハラやパワハラに配慮しなければならなくなったために、言動
を必要以上に抑制してしまうようになっている。
このような様々な要素に、適切に対応できとしたら、もはや超人だ。
だが、そんな超人ばりの働きを求められているのが、最近のマネー
ジャーの現実なのだ。
★このメルマガをでアップ・グレードする・・・
ココ→ http://www.kfujii.com/tcy06.htm
★本書の詳細、お買い求めは、
→ http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4862483658/tachiyomi
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■■選書コメント
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本書は、タイトル通り、上司の在り方、仕事の仕方を説いた本です。
激動の時代の中で、上司がどのように部下と接し、やる気を引き出
し、成果を上げていけばよいのかを説明してくれます。
マネジメントを説いた本は、古今東西、すでにたくさん発刊されて
きました。しかし、昨今は、事情が大きく変わってきています。
当然、求められる上司の姿も変わってきています。本書は、そんな
環境変化にあわせて大きく変化を求められている上司の在り方を書
いた本です。
新書で薄い本ですが、思いのほか情報は詰まっています。内容も、
単なる抽象論でなく、具体的な処方箋まで明示されていて、極めて
実用的かつ実践的です。
また、従来の上司本の多くは、読んでも上司本人自分ではどうしよ
うもないことばかり書いてありました。書かれたことを実践しよう
すると、会社の制度を変更しなければならなかったのです。
しかし、上司には、そのような権限はありません。結局、上司本は、
制度を変える権限を持つ経営者や人事担当者でなければ生かせない
ことが多かったのです。
あとは、部下のやる気を引き出す会話術や仕組みなど、枝葉末節の
テクニックを説いた本が大半でした。
その点、本書には、具体的なマネジメントの手法がしっかり書いて
あります。しかも、会社の制度を変えることなく、現場レベルでで
きることばかりです。
上司になったばかりの人や、これから上司になる人はもちろん、長
くマネジメントの立場にいて、ベテランの域に達する人まで、すべ
ての上司にお勧めします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎このマガジンは、著者と出版社から掲載許可をいただいて配信し
ています関係で、無断転載はできません。ご了承ください。
──────────────────────────────
◎バックナンバー→ https://www.bbook.jp/backnumber
◎ご意見、お問い合わせ、→ info@kfujii.com
◎登録、変更、解除→ https://www.bbook.jp/mag.html
──────────────────────────────
発行元:藤井事務所 責任者:藤井孝一 (C) Copyright 1999-2009
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━