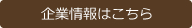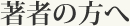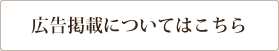無料版・バックナンバー
- ビジネス選書&サマリーのバックナンバーをご覧いただけます。

2013/02/15
超情報化社会におけるサバイバル術 「いいひと」戦略
-

評価経済社会がやってきた
ネットの発達で、誰もが同じ情報を見ることができるようになり、シェアされる速度も速くなった。あらゆる情報が短時間で共有される「ハイパー情報化社会」になったのだ。このような社会では、モノやサービスに対する「評価」も情報としてたくさん流通している。貨幣と商品を交換し合う貨幣経済社会に対し、評価と影響を交換し合う「評価経済社会」だ...
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■今週の選書
■超情報化社会におけるサバイバル術 「いいひと」戦略(岡田斗司夫)
■マガジンハウス
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★本書の詳細、お買い求めは、
→ http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4838724063/tachiyomi
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■■選書サマリー
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
評価経済社会がやってきた
【1】
ネットの発達で、誰もが同じ情報を見ることができるようになり、
シェアされる速度も速くなった。あらゆる情報が短時間で共有され
る「ハイパー情報化社会」になったのだ。
このような社会では、モノやサービスに対する「評価」も情報とし
てたくさん流通している。貨幣と商品を交換し合う貨幣経済社会に
対し、評価と影響を交換し合う「評価経済社会」だ。
ここでは、お金よりも評価が価値を持っている。いいことをした人
の評価は高まり、逆に悪いことをした人の評価は、どんどん下がっ
ていく。
今後、貨幣経済社会は徐々に力を失い、数年後には評価経済社会と
入れ替わるはずだ。その兆しは既にある。Amazonのレビューやヤフ
オクの利用者評価機能は、物や人を評価するシステムのさきがけだ。
【2】
人類の歴史は、時々「家柄社会」になったり、「実力社会」になっ
たりしてきた。しかし、基本的には「評価社会」の時代が大半を占
めていた。
大昔の中国や日本も「評価社会」だった。たとえば三国志時代の中
国では、難しい話をしたり、親孝行をしたりして徳を高めると、地
元の名士から中央への士官を推薦してもらえる仕組みだったのだ。
そんな仕組みに不満を抱いた曹操は、才能さえあれば官吏として登
用する制度を採用した。しかし、当時の知識人からは反発を受けた
と言われている。
一方、日本では、平安・鎌倉・室町時代が「評価社会」だった。ど
んな家柄に生まれたかで、就ける役職が決まった。このような社会
を「身分社会」と呼ぶ。言い換えれば「評価社会」だ。
戦国時代では、織田信長が才能による人材登用を行った。その後、
徳川家康が評価社会に戻す。社会が安定している時は、徳や人格が
重視される「評価社会」、不安定な時は「実力社会」になるのだ。
【3】
私たちが経験しているのは「評価経済社会」だ。昔の人々が経験し
た評価社会に「経済性」が加わったものだ。違いを端的に言えば、
田舎の評価が、都会でも同じように通用するかどうかだ。
評価社会では、田舎で得た評価が、都会で同じように通用するわけ
ではない。田舎で高い評価を得ても、都会に行けば全然通用しない
ということはよくある。
才能は、判別するのに時間がかからない。だが、人格はすぐに分か
らない。本人のスゴさを説明してくれる人や、証明してくれるもの
がないと評価できないのだ。
しかし、評価経済社会は違う。田舎で得た評価が、都会でも同じよ
うに通用する。それは評価という「通貨の兌換性」を保証するもの
が現れたからだ。
Twitterやfacebookと言ったソーシャル・ネットワーキング・サー
ビスで得た評価は、今、暮らしている場所から離れ、地球上のどこ
にいても通用する。
ネットにアクセスして、Twitterのフォロワー数やfacebookの「い
いね!」の数を見れば「実はスゴい人だったんだ!」と分かる時代
なのだ。
【4】
今、私たちが生きている社会では、評価経済が1位で、貨幣経済は
2位だ。それは、Amazonを見れば一発で分かる。Amazonには、マー
ケットプレイスという中古市場がある。
そこは、とにかく安い。かといって、一番安い本を買うのかという
とそうではない。多少、高くても、評価の高い古本屋さんから買う。
安いのには、それなりの理由があると考えるからだ。
Googleに勤めていた技術者たちが、facebookに転職している。理由
は面白そうだからだ。技術者たちは、労働条件より面白い仕事を取
る。技術者仲間の「評価」の方が「お金」よりも強い動機なのだ。
今後、私たちは、お金を稼ぐために働くことに情熱を捧げられなく
なる。お金は、もはや終わってしまったコンテンツ、いわゆる「終
わコン」になってしまったのだ。
★本書の詳細、お買い求めは、
→ http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4838724063/tachiyomi
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■■選書コメント
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21世紀の超情報社会で生き延びるためには「いいひと」であるべき
です。どうすれば「いいひと」になれるのか、個人が生き延びる戦
略としての「いいひと戦略」を教えます。
自己啓発書にありがちな「いい人」のススメではありません。もち
ろん、ただ「いいひと」ぶるのとも違います。信頼に足る人物との
評価を得るために、戦略的に「いい人」になるのです。
著者は、オタキングやダイエット本『いつまでもデブと思うなよ』
などで有名な社会評論家の岡田斗司夫さんです。ユニークな視点と
切り口はさすがで、世相をズバリ解説してくれます。
本書は、最近のビジネス書に多いコラム集でも、ハウツーを書き連
ねたものでもなく、頭から通読したい、論旨のしっかりした本です。
何でもセミナーを書籍に書き起こしたものだそうです。
「コミュニティにコミットする」とか「大事なのは人格」「コンテ
ンツは落ちている」など、斬新な視点に「なるほど」とうならされ
れます。
と言っても、難しい本ではありません。テレビでお馴染みのお笑い
芸人から、市井やネットの有名人など、バラエティに富んだ事例と
ともに解説してくれます。
テーマである「いい人戦略」「イヤな人戦略」にはじまって「評価
経済社会」「キャラクター上場」など、コンセプトだけでなくネー
ミングも秀逸で、楽しませてくれます。
読めば、ソーシャルメディアの時代に、何が起きているのかがよく
わかります。読んだ後でしっかり考えれば、これからの生き方のヒ
ントがたくさん見つかるはずです。あらゆる人にお勧めします。
★本書の詳細、お買い求めは、
→ http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4838724063/tachiyomi
──────────────────────────────
◎バックナンバー→ https://www.bbook.jp/backnumber
◎ご意見、お問い合わせ、→ info@kfujii.com
◎登録、変更、解除→ https://www.bbook.jp/mag.html
──────────────────────────────
発行元:(株)アンテレクト 藤井孝一 Copyright 1999-2013
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━